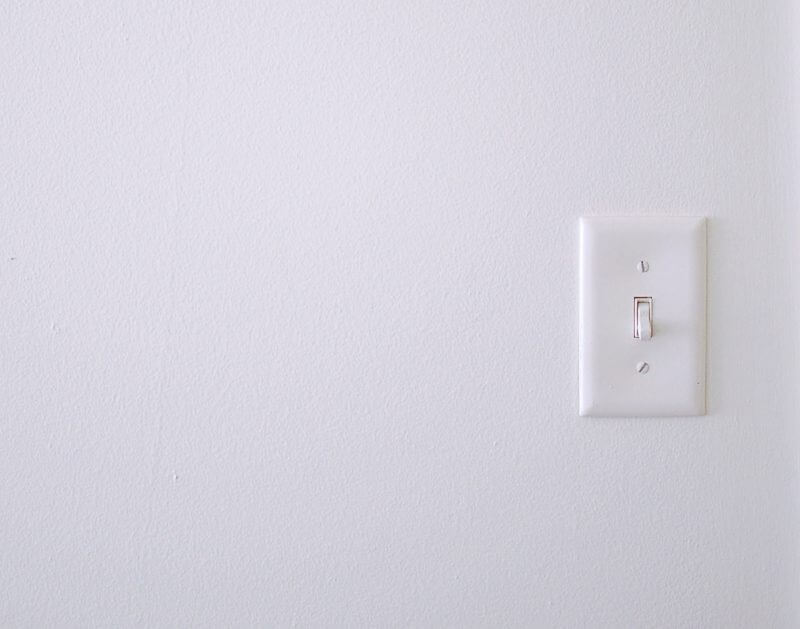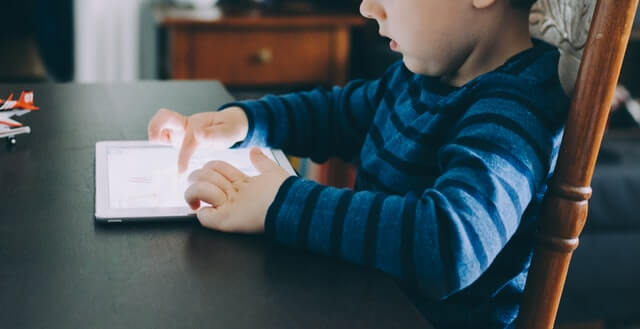中学受験は親が勉強を見るのはNGという塾も結構あり、見てはいけないのではと悩みどころです。
ただ、5年生1学期あたりまでは中学受験に向けて親が勉強を見るのは良いと思います。
もちろん、塾でガッツリ見てもらう余裕がある、自分で問題解決できるという子であればいいでしょう。
しかし、家庭によっては余裕がない、子供が頼りないから親が勉強を見ることがあります。
実際に中学受験を検討し、5年生まで親が勉強を見るスタンスで学習してきたうちの例を取って紹介していきます。
中学受験で親が勉強を見るのは〇!理由は3つ
中学受験で親が勉強を見るのはOKだと思います。
以下の3つの理由は結構大事なので、おさえておいてください。
①中学受験の時点で忙しいのにスケジュール管理・どこがわからないのかすべて把握は自分でできない
中学受験で親が勉強を見るのがおすすめな理由は…
-
- 勉強の進捗状況を把握しやすい
- どこがわからないのかすべて把握できる
- 子供は自分で完璧に管理できない
からです。
中学受験ではいくら時間があっても足りないと思います。
その状態で、子供が中学受験までのスケジュール管理をするのはかなり厳しいです。
親が勉強を見ていれば、今どこまでできていて、どこがわからないのか、どこを繰り返し解いた方が良いのかがわかります。
子供は自分で同系統の問題を見つけることができませんし、その時間ももったいないです。
また、親が勉強を見る=答え合わせというわけではありません。
ここで言っている親が勉強を見るというのは、実際に親が問題も解いて理解して説明するまでを言っています。
何となくで教えてしまうと子供もしっかり落とし込みができません。
わかったと言いながら、実はわかっていないことが多いんです。
なので、ものぐさせずに親も問題を解いてみましょう。
問題を解いてわからないところを教えることで、どこが弱いのか把握しやすいくなります。
※塾、問題集の解き方で教えるようにしましょう。
これは中学受験では方程式が使えないからです。
②中学受験で親が勉強を見るのは手間がかかるからやりたくないは逃げ!子供のサポートをしよう
塾で親が勉強を見るのはやめてくださいと言われるかもしれません。
でも、これは完全に丸投げというわけではないですよ?
塾で親が勉強を見るのはNGと言っているのは、解き方を教えるのがダメということです。
親がものぐさをしてノータッチはやめてください。
親が勉強を見なくても、勉強しやすい環境を作る、子供の体調管理をする、スケジュールを一緒に計画立てる、わからないところがあったら一緒に悩むことはしてあげましょう。
親が寄り添うことで子供は不安が減ります。
プレッシャーばかりかかると子供はつぶれてしまうので、心のサポートが大事です。
塾に丸投げは絶対やめましょう。
③中学受験で親が勉強を見ないとやらない子は多い!
中学受験は親が勉強を見ないとやらない子は多いです。
上記の通り、自分から進んで勉強するという子はなかなかいません。
もちろん、六年生になると焦りもあり、自主的にやり始めたり、習慣化ができているでしょう。
それでも、ゲーム、YouTube、漫画に逃げる子も多いです。
うちは多かったですね。
なので、親が勉強を見る、むしろ、一緒に解いて悩むくらいのことをしないと受験まで続きません。
もちろん、息抜きは必要なので柔軟に対応するようにしてください。
中学受験で親が勉強を見る場合の注意点
中学受験で親が勉強を見る場合の注意点がいくつかあります。
上記の点と合わせて覚えておきましょう。
①中学受験で親が勉強を見るのは基礎までが良い!自分で取り組もうという気がなくなるから
中学受験で親が勉強を教えるのは基礎までが良いです。
ちょっと難しい応用が出てきたらすぐに「わからないから教えて」となるようでは、中学受験に挑めません。
すぐに親に頼る癖が抜けないのは避けたいですよね。
自分でじっくり時間をかけて、基礎知識をフル回転させて解くことも大事です。
うちは下剋上受験を一緒に解いていたんですが、最初は一緒に解いて、解説を見て、やり方を覚えてを繰り返していました。
しかし、途中から自分でじっくり考えて、閃いて解けた!となったときは本当に嬉しそうでした。
そこからどんどん自分で解くようになったんです。
自分一人でもできるという自信にもつながるので、一人で取り組むということも大事だと思いました。
もちろん、どうしても解けないという場合は手を貸して良いと思いますが、じっくりやらせてみてください。
②中学受験で親が勉強を見る=全部教えるではない!ヒント&声掛けなら自分で考える
上記と似てしまいますが、親が勉強を見る=全部教えるではありません。
覚えなくては解けないこともありますが、そこからは自分の力でやらないと伸びないでしょう。
どうしてもわからないという場合は、ヒントや声掛けをしてみてください。
そこから自分でどうやって解いたらいいのか、導き出せることが多いです。
うちでもすぐに「わかんない、わかんない」と言って頼ってましたが、ヒントを与え親がじっくり我慢して待っていました。
やっぱり解けました。
「ほら解けるでしょ!」、「すごいじゃない!こんな難しいのお母さんも解けないよ?」と褒めています。
これで子供の気分も上がるんですよね。
だからこそ、ヒントを与える、声掛けって大事だと思います。
③中学受験の問題がどうしても解けない!解説を一緒に読もう
前述していますが、中学受験の問題がどうしても解けなければ、解説を一緒に読んでOKです。
もちろん、基礎の問題を解く場合はまず時間をかけて悩ませましょう。
しかし、応用だとどうしても解けないという場合があります。
10~15分悩んでも解けない、閃きがまったくないという場合は、解説をよく読んで理解させてください。
その後に再度、問題を解く、似たような問題を解くのがおススメです。
④中学受験の問題を解きっぱなしにさせない!親が勉強を見るのはココが大事
中学受験の問題を解きっぱなしにすることってよくあります。
よくわからないで、解説を見る、解けた気になって終了ということありませんか?
解きっぱなしでは違う種類の問題をたくさん解いても、身につきません。
-
- よくわからない
-
- 解説を見る
-
- 実際に見ながら解いてみる
-
- 見ないで解いてみる
-
- 解けたら似た問題を解いてみる
ここまでやって解けるようになっていればOKです。
解きっぱなしではなく、ここまでやってください。
ここまでやらないと身につかないので、時間がなくてもやる必要があります。
焦ってあちこち手を付ける方が伸びません。
④勉強は机に向かってだけじゃない!テレビ・本・博物館などをフル活用してつまらないをなるべく避ける
勉強は机に向かってだけではありません。
-
- テレビで時事ニュースをみて家族で話す
- 本で読んだ知識を話してみる
- 博物館で学んだことを書き出してみる
ということも力になります。
もちろん、六年生の2学期になるとここまで余裕がないと思うので、6年生になる前までは上記のような勉強法を取り入れてみると良いでしょう。
実際にうちでも上記のような勉強をして、飽きないように工夫しました。
苦手意識もなるべくつかないようにしたかったのですが、有効でした。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
中学受験の社会理科は5年生からがおすすめ!理由は3つはこちら>>
中学受験で親が勉強を見るのは基礎まで!後はスケジュール管理が重要
中学受験で親が勉強を見るのは上記の通り、基礎までが良いでしょう。
それでは高学年になってから親がやるべきこととは何か…やはり中学受験で親が勉強を見るというよりも、スケジュール管理が重要です。
スケジュール管理について、詳しく掘り下げていきます。
①週単位で管理する【ざっくりでOK】
中学受験のスケジュール管理と言っても月単位はざっくりしすぎており、ここは子供に任せても良いでしょう。
親子でチェックする程度でOKです。
というのも、塾で何をするのか出るはずなので、それくらいは子供も把握し、自分で割り振ることを考えさせてください。
現実的に重要なのが、中学受験に向けて週単位でのスケジュールです。
ざっくり月単位でこなすべきことがわかったら、今週は何をすべきかの見直しをしましょう。
-
- 塾のスケジュール(何をやっていくのか)をチェック
- 子供の勉強を見て何がわかっていないのか(塾でのテスト、自宅学習で間違いが多いところ)をチェック
この2点はおさえてください。
また、塾のスケジュールに合わせて、テストや自宅学習でわからなかったところを洗い出し、まとめて問題を解く時間を入れます。
1週間のスケジュールではどの日にどの教科を勉強するかをざっくり決めておくだけでOKです。
親が勉強を見るのではなく、勉強しているかをチェックするという感じになります。
②中学受験に向け余裕をもってスケジューリングする
塾のスケジュールに合わせて、中学受験の勉強は余裕をもって時間を取ります。
というのも…
-
- 学校の行事やその他のイレギュラーなことが入る可能性がある
- 体調を崩す場合がある
からです。
意外とイレギュラーなことが入ったりするので、余裕をスケジューリングしないと後半がきつくなります。
中学受験では親が勉強を見るのではなく、うまくスケジュールを組んでいってあげるのが成功につながるんです。
③1日単位のスケジュールは何をどこまで勉強するのかを決める【達成できなくても怒らない】
最も大事なのは1日のスケジューリングです。
1日単位でのスケジューリングは…
-
- どの教科をどこまでやるのか決める
- 上記で洗い出したわからないところを組み込む
ようにします。
最初はうまく回らず達成できないことが多いです。
だからといって、ここで達成できないことを怒るのはやめてください。
また、達成できるまで勉強させるということもNGです。
睡眠時間が短くなる、長時間勉強は疲労に繋がり、頭の回転が悪くなります。
早く寝かせて、早く起こす方が良いです。
最初のうちはうまくいきませんが、徐々にこなせるようになります。
また、早く寝かせているので、うちのスケジュールでは朝も勉強時間に活用しています。
-
- 朝の7時まではご飯と好きなことをする
- 朝の7時から学校に行くまでの時間は勉強をする
としています。
また、帰ってきてからもすぐに勉強すると疲れる、ストレスがたまるので、一休憩してから勉強する流れです。
このやり方でも徐々に予定で組んだものをこなせるようになります。
小学校6年生になるとそこまで余裕をもってできませんが、少しでもストレスをためずに進めるにはおすすめです。
④スケジュールを組んでみて間に合わない?最終的には受験する中学校を高望みしないのが良い
中学受験は誰でも希望の学校に入れるわけではありません。
むしろ、入れない子の方が多いでしょう。
6年生でスケジュール通り勉強し模擬試験を受けて、明らかにレベルが届かない学校を目指すのはおすすめしません。
というのも、受験はそこまで甘くないからです。
また、6年生になるといくらスケジュール管理しても時間が足りないということが多いでしょう。
どこのうちでも必死なのでますます厳しいと思います。
また、何とか入れたとしても、ついていくのが大変…というリスクがたかくなるので、死に物狂いで勉強を続ける必要があります。
だからこそ、頑張って入れる、手に届くかもしれないという学校を勧めるのは親の役目かなと思います。
さらに最終的に中学受験をするかどうかの検討をする必要もあるかもしれません。
どのタイミングで決断すべきかについては、別記事で詳しく書いています。
中学受験をしない勇気!子供がストレスを感じたら決断はこちら>>
中学受験で親が勉強を見るのはNGとする塾は多いです。
しかし、塾の解き方など、おさえるべきポイントをわかっていれば、中学受験で親が勉強を見るのはおすすめ。
中学受験は親子で挑むものなので、子供に寄り添って一緒に乗り切ってください!